※このサイトは楽天インシュアランスプランニング株式会社が運営し、掲載する保険会社に一括して見積もりを依頼するサービスを提供しています。

最終更新日 :2025年1月30日
「新車特約(車両新価特約)」とは、車を新しく購入した際に加入する車両保険に付帯できる特約のひとつです。この特約を付帯すると、車両保険の支払い対象となる事故で車が大きな損傷を受けた場合でも、「修理費用」ではなく「新車の再購入費用」が補償されることがあります。
車を修理するのではなく、買い替えができるというメリットがありますが、そのぶん保険料の負担も増えるため、ご自身の車に必要かどうか迷う方もいるかもしれません。
この記事では、新車特約のメリットや必要性、適用されるケースや適用されないケース、適用後の等級ダウンなどのデメリットについてわかりやすく解説します。

新車特約(車両新価特約)とは、そもそもどういう特約なのでしょうか。ここでは、新車特約の概要と付帯できる条件などを解説します。
新車特約(車両新価特約)とは、車の任意保険である車両保険に付帯できる「特約(オプション)」のひとつで、複数の保険会社が提供しています(名称は保険会社により異なります)。
この新車特約を適用するには「車両保険に加入していること」が前提となります。
これは、車両保険から事故の保険金が支払われるからです。一般的には、初度登録から2~3年の車が対象となります。この特約を付帯していると、万が一事故などで車が大きな損傷を受けた場合でも、車を「修理」するのではなく「買い替え」できるというメリットがあります。
車両保険に新車特約を付帯できるのは、新車あるいは初度登録から一定期間内の車です。具体的にはいつまで(何年目まで)の車が適用されるのでしょうか。また、期限などはあるのでしょうか。
年数や期間は保険会社によって異なりますが、一般的には、初度登録から2年目~3年目以内の車を対象にしているようです。保険会社が設定する期間内であれば、中古車でも新車特約を付帯できます。
車が事故で大きな損害を受けた場合について、車両保険に「新車特約をつけている場合」と「新車特約をつけていない場合」の違いをみていきましょう。
一般的には、車両保険で損害の補償はされますが、車両保険で補償される上限額(車両保険金額)は、事故を起こしたときの車の市場価格がベースになります。しかし、新車特約を付帯していれば、新車価格相当額(新車購入時の価格)で補償を受けられます。
たとえば、以下の図のように、新車価格相当額(新車購入時の価格)が「400万円」であり、新車特約を付帯していないとします。2年目に事故を起こしてしまい、そのときの市場価格は「340万円」であるため、この市場価格をもとに車両保険金額(車両保険の補償上限額)は「340万円」となります。
購入してから1年、2年……と経過するにつれて、市場価格は下がっていきます。しかし、車両保険に新車特約を付帯すると新車購入費用「400万円」が補償されることがあります。
新車特約を付帯した場合の補償イメージ

新車特約は対象車両の再取得費用や修理費が支払われる特約です。再取得費用には車両本体価格だけでなく、付属品や消費税も含まれます。一方、納車費用などの諸費用や、消費税以外の税金、自賠責保険料などは含まれません。
また、新車特約が適用される場合は、新車価格相当額を限度として支払われます。そのため、車両本体価格と付属品・消費税の合計額が新車価格相当額を超えるときの差額は自己負担となります。
なお、車両保険の必要性や保険金額の決め方などを詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
保険金がどのように支払われるかについて、もう少し詳しく説明しましょう。
たとえば、下の事例で、250万円で購入した「新車特約をつけていない」車が事故を起こした場合、車両保険からは150万円が支払われますが、250万円と150万円の差額の100万円は自己負担になります。
一方、「新車特約をつけている」場合は、250万円と150万円の差額の100万円が新車特約から支払われることになり、250万円を上限に保険金が支払われます(なお、車両保険に免責金額を設定している場合は、免責金額を差し引いた額となります)。
ただし、全ての保険会社が新車特約を取扱っているわけではありません。保険会社によっては、新車特約を付帯できないこともありますので注意が必要です。
車が大破し、新車を買い替える場合


新車特約と似ている全損諸費用特約とは?
新車を購入してから間もなく、事故などで車が大きな損害を受けてしまったら経済的にも心理的にもダメージが大きいですよね。しかし、新車特約を付帯して、同じ車を買いなおすことができれば自己負担の費用が軽減されるでしょう。
なお、契約の際に設定した新車価格相当額の範囲内であれば事故車と違う車種を買いなおすことも可能です。
また、新車特約と補償内容が似ている特約として、事故で車が全損になってしまったときに支払われる特約である「全損諸費用特約」があります。一般的に、廃車や買い替え費用を車両保険の10%(20万円が限度)で補償されることがあります。
「全損諸費用特約」は、保険会社によって、自動で車両保険に付帯している場合もあれば、任意で付帯しなければいけない場合もあります。また、新車特約より補償の金額は低くなり、「全損諸費用特約」と新車特約を併用することはできないためご注意ください。

車両保険に新車特約を付帯しておけば、どのような事故でも新車相当額の補償が受けられるのでしょうか。保険金が支払われるためには、いくつかの条件があります。新車特約の補償を受けるための具体的な条件をみていきましょう。
補償対象になるのは、契約している車が車両保険の支払い対象になる事故で大きな損害を被った場合です。一般的には、事故で「半損」から「全損」の損害を受けた場合が該当します。
具体的には、「修理できないほど損害を受けた」「車の市場価格よりも修理費がかかる」「修理費が新車価格相当額の50%以上」といった場合などに、新車価格相当額を限度に支払われます。
なお、一般的に、「盗難」については対象外となりますが、盗難に遭った車が発見され、車が全損または半損状態となっていた場合には、新車特約が適用されます。
【補償対象となる損害状況のケース】
※細かな条件は保険会社によって異なります。

次のケースでは、新車特約が適用されません。
【新車特約が適用されないケース】
盗難は、車両保険では補償対象ですが、新車特約では対象外です。ただし、盗難に遭った車が後日発見され、全損もしくは半損状態になっていたときは適用されることがあります。
また、タイヤのみパンクしたときや、法令により禁止されている改造をおこなった部分が損害を受けたときなど、車の本質的構造部分以外が故障したときも新車特約は適用されません。
そのほか、修理費が新車価格相当額の50%未満のときや、無免許運転、酒気帯び運転のように保険契約者などの重大な過失による事故のときも、新車特約の補償対象外となります。
また、車に欠陥があったときや自然消耗により車に損害が生じたときも、新車特約は適用されません。たとえば、初期不良やサビ、摩耗、腐食などは、新車特約の補償対象外です。

新車特約を付帯できる車種に制限はある?中古車や新古車も対象?
新車特約を付帯できる車について、少し解説します。
一般的に、新車特約の対象となる車両は、車両保険の対象となる自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用軽四輪貨物車・自家用小型貨物車などです。いわゆる自家用の普通自動車や軽自動車などが該当します。ただし、保険会社によっては、自家用普通貨物車・キャンピングカーも対象になる場合があります。
また、新車特約は、新車だけでなく新古車や中古車も対象です。初度登録から11ヵ月以内、25ヵ月以内、61ヵ月以内などの保険会社が定めた期間の車が対象になります。継続して付帯する期間も保険会社によって決められています。初度登録からの期間や継続期間については保険会社に確認しましょう。
なお、新車特約は補償期間中であれば変更できるため、途中で不要となれば、新車特約を外すことは可能です。加入した保険会社に連絡して、手続きを進めましょう。

車両保険に新車特約を付帯することができる場合、新車特約を付帯するべきでしょうか。「新車特約をつける」「新車特約をつけない」の間で判断に迷うことがあるかもしれません。以下のような場合は新車特約を付帯する必要性・メリットがあると考えられます。
【新車特約を付帯するメリット】
以下でそれぞれみてみましょう。
新車特約を付帯すると良いと考えられる例のひとつは「補償の対象にする車が新車の場合」です。新車価格相当額(新車購入時の価格)を限度に補償されるため、「新車を購入して間もないのに大きな損害を受けてしまった!」といったときでも補償を受けられます。
仮に事故で新車が全損になったとしても、保険金を利用すれば同等の車を再購入できます。
新車特約を付帯すると良いと考えられる例としては、「高級車を購入した場合」もあげられるでしょう。
たとえば、高級車を購入した場合、購入してから2年、3年と経過していくうちに、新車購入時の価格から大きく下がっていきます。
しかし、新車特約は新車価格相当額(新車購入時の価格)を限度に補償されるため減価償却される金額が大きく、市場価格の下落スピードが早い車に適しているといえるでしょう。
新車特約で補償される上限額である新車価格相当額は、初度登録からの経過年数が少ないほど高額に見積もられます。そのため、初度登録から長期間経過していると、車両保険の保険金額は新車価格よりも低くなる可能性があり、自己負担が発生するかもしれません。
しかし、新車特約を付帯していれば、新古車・中古車が事故で大きな損害を受けたとしても買い換え費用を保険金でカバーできます。また、自己負担が発生する場合でも新車価格相当額が高く設定されている分、自己負担額をおさえやすくなるでしょう。

ローンが残る車で事故を起こした……新車特約の必要性は?
自動車ローンなどで車を購入する場合がありますよね。そのような場合も、新車特約の必要性が高いといえます。事故を起こしてしまって車が廃車になっても、自動車ローンの残債があるためです。新車特約の保険金では、ローンの残債にあてることはできませんが、車を買いなおすことができるため、損害をおさえることができるのです。
また、運転に自信がない、事故後には車を買いなおしたいが車のグレードは下げたくない、と考える方にとっても新車特約は必要性が高いといえるでしょう。
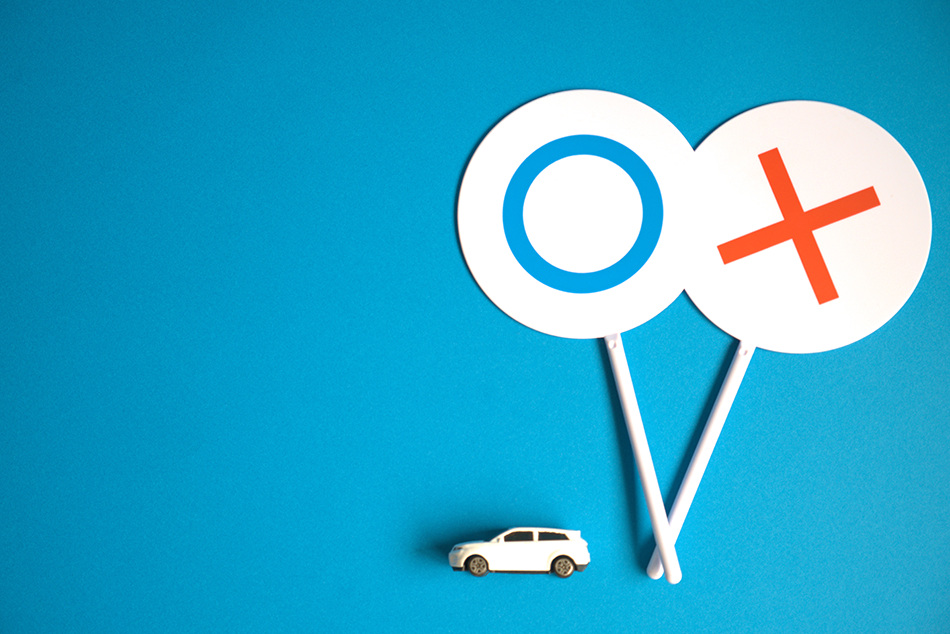
新車特約を付帯すると前述のようなメリットもありますが、デメリットとして以下の点もあげられるため確認しておきましょう。
【新車特約を付帯するデメリット】
新車特約を付帯しておくと、万が一のときに安心できますが、そのぶん保険料は上がります。一般的には、保険金額が大きく、車を購入してから年数が経過するほど、保険料が高くなります。
たとえば、初度登録から1年目と5年目の場合を比較すると、後者の保険料のほうが一般的には高くなります。
自動車保険の保険料が決まる重要な要素のひとつに「等級制度(ノンフリート等級制度)」というものがあります。これは、自動車保険の契約者の事故歴(保険金の請求歴)に応じて保険料の割増し率や割引き率を決める制度です。
下図のように1等級~20等級と20区分に分けられており、1等級~4等級は割増し率、5等級~20等級は割引き率が適用されます。
「事故ありの割引き・割増し率」は、等級ダウン事故を起こした方に適用されます。同じ等級であっても、無事故の場合よりも割引き率が低くなり、3等級ダウン事故を起こすと、3年間は「事故ありの割引き・割増し率」が適用されます。
新車特約を利用した場合でも、翌年度から等級が3等級ダウンし、下図の「事故ありの割引き・割増し率」が適用されます。
つまり、新車特約を適用すると、3等級ダウン事故を起こした場合と同様の扱いとなるため、翌年度から保険料が高くなる点に注意する必要があります。
等級が上がるほど保険料の割引き率が高くなる

契約している車の内外装、外板部品などのみに損害が生じている場合は適用されません。新車特約が適用されるのは、エンジンやフレームなど、車の重要な構造部分に損害が生じた場合です(補償対象になる損害箇所は、保険会社で異なります)。
「無免許運転、酒気帯び運転などで生じた損害」「地震・噴火またはこれらによる津波で生じた損害」「契約している車の欠陥、さび、摩滅、腐食など自然消耗で生じた損害」「故障で生じた損害」なども、補償の対象外となっています。
このように全てのケースで補償を受けられるわけではない点を理解しておかなければいけません。

台風や洪水などで車が大きな被害を受けた!新車特約は使える?
台風や洪水などによる被害では、どうなるのでしょう。気になりますね。 基本的には、車両保険の補償の範囲内であれば、これらによる被害も補償されます。したがって、 新車特約についても、構造部分に50%の損害が生じていれば、一般的には台風によって車が破損したり、洪水で車が水没したりした場合でも補償の対象となります。
ただし、地震、噴火、津波によって生じた損害は、新車特約の補償対象外です。保険会社によっては、地震や噴火、津波による車の被害に対応する「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」※1を提供しているところもあります。万が一に備えたい方は、検討してみましょう。
※1 名称は保険会社によって異なります。

損害保険料率算出機構によると、自家用普通乗用車のうち、自動車保険の対人賠償の加入率は82.6%※2、対物賠償の加入率も82.6%※3です。特約を付帯することで、自動車保険による補償をさらに追加することができます。ここでは、新車特約以外の特約をいくつか紹介します。
【おもな自動車保険の特約】
ただし、保険会社によっては特約の名称が異なることや、該当する特約が存在しないこともあるため注意が必要です。以下で詳しくみていきましょう。
※2 2023年3月末時点。
※3 参考:損害保険料率算出機構「2023年度 自動車保険の概況」
「弁護士費用特約」とは、もらい事故など偶然の事故により被害に遭い、相手への損害賠償請求のために弁護士費用や法律相談費用がかかったときに適用される特約です。
もらい事故は保険会社が直接示談交渉することができないため、外部の弁護士に依頼することが一般的です。費用負担を軽減するためにも、弁護士費用特約を検討しましょう。
弁護士費用特約についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
一般的に、地震や噴火、津波による車の損害は、車両保険の補償対象外です。このような損害に備えたいときは、「地震・噴火・津波車両全損時一時金の特約」を検討しましょう。
この特約では、地震・噴火・津波により契約車両のフレーム、サスペンション、原動機など所定の部位に損害が生じたときや、流失や埋没により発見されなかったとき、また、車両が運転席の座面を超えるなど一定以上の浸水被害にあったときなどに一時金が支払われます。
「ファミリーバイク特約」とは、原動機付⾃転⾞使⽤中の事故による相手への賠償やケガに対応する特約です。被保険者だけでなく、一定条件を満たす家族も利用できます。
保険会社によって異なりますが、⼈⾝傷害型と⾃損傷害型があり、自損傷害型を選択した場合はほかの車との接触によるケガは補償対象外となります。そのため、幅広いケースに備えたい場合は人身傷害型を検討しましょう。ファミリーバイク特約についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
個人賠償責任特約とは、日常生活における偶然の事故により法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる特約です。たとえば、他人にケガをさせたときや、他人の所有物に損害を与えたときなどに適用されます。
この特約はファミリーバイク特約と同様、一般的に被保険者だけでなく、一定条件を満たす家族も利用できます。
「対物全損時修理差額費用補償の特約」とは、対物事故で相手の車の修理費が時価を超え、被保険者がその差額を負担したときに一時金が支払われる特約です。ただし、差額として負担した金額が一時金よりも少ないときは、差額負担額が上限として支払われます。
「レンタカー費用補償の特約」とは、対象車両が事故に遭い、保険会社が指定するレンタカー会社から代車を借りたときに適用される特約です。ただし、1日あたりの上限があるため、上限額を超えたときは自己負担する必要があります。
レンタカー特約についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
「鍵交換費用の補償」とは、対象車両のカギの盗難・紛失があったときに、かかった費用が支払われる特約です。また、車両が盗難された後に手元に戻り、盗難防止のために鍵を交換するときにも適用されることがあります。

自動車保険を見直すときには、複数の保険会社を比較することがおすすめです。
しかし、複数の保険会社に見積もりを依頼するのは手間がかかります。手間をかけずに比較するためにも、一括見積もりサイトを活用してみてはいかがでしょうか。
自動車保険一括見積もりサイトなら、同じ条件で複数の保険会社に見積もりを依頼できます。ぜひ一括見積もりをしてご自身に合う自動車保険をみつけてください。
「新車特約」は車両保険に付帯できる特約です。新車特約を付帯すると、事故で新車や初度登録からの期間が短い新古車・中古車が全損、または半損したときや損害額が車両保険金額を上回ったときなどに、新車購入時の金額相当の補償を受けることができます。
とりわけ、新車や高級車を購入した場合などにメリットがある特約です。なお、全てのケースで付帯できるわけではなく、初度登録から一定期間内の車のみに適用されたり、補償を受けられる事故が限定されていたりするなど、いくつか条件があります。
また、車両保険では「盗難」は補償対象ですが、新車特約では一般的に補償されない点にも注意しましょう。
このような新車特約の特徴を理解したうえで付帯するかどうかを検討すると良いでしょう。

生命保険会社に約8年勤務後、住宅建築の建設会社に19年勤務。現在も建設会社で住宅取得資金や住宅ローンアドバイスを行う。また、ファイナンシャルプランナーとして、ライフプランをもとにした教育資金や自営業者の老後資金、保険見直しなどのアドバイスを行う。主婦・母・自営業の嫁・親の介護の経験を活かし、相談を受けている。
(地域密着型・お客様に寄り添うFP)
https://takasugi-fp.com
【保有資格】
CFP®(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、住宅ローンアドバイザー
※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
※このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問い合わせください。
※税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの最終更新日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
( 掲載開始日:2022年12月28日 )
2412678-2512
最短5分から
1番安い自動車保険を見つけよう!